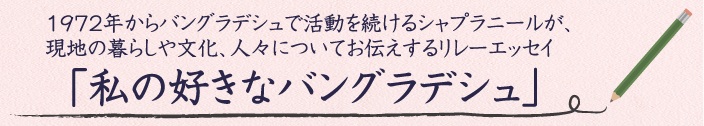
私が初めてバングラデシュを訪れたのは、社会人3年目。学生時代、女一人旅では選択肢から外さざるを得なかった国に、シャプラニールのスタディツアーで足を踏み入れた。ダッカを離れて村に向かう中、河を遡る船で感じた風、植物の匂い、河と湿地と緑の水平線。苦手なスケッチに挑戦している背後にできた黒山の人だかりから聞こえた「これはなんだ?」「あのニワトリじゃないか?」「いやいやあの犬だろう」(想像)おじちゃんたちの声。明かりひとつ見えない真っ暗なあぜ道を歩いて参加した女性ショミティで、サリーで顔を隠しながらこちらを見つめる大きな目。そこには、それまで訪れた中国、タイ、ネパール、スリランカとは異なる豊かな水と緑に溢れた風景と人々の姿があった。
 学生時代から、南アジアに心惹かれてはいた。でもそれを決定づけたのは、このバングラデシュの旅だった。会社で医薬品研究に携わっていた私は、この旅をきっかけに南アジアの農村にどっぷりとつかっていった。畑や田んぼを牛の力を借りて耕し、ヤギを飼い、羊を束ね、ニワトリを放つ。人びとの暮らしは常に家畜とともにあるが、近しいその存在への感謝は、その命を自らの命を続けるために食することで示される。家の庭先で、市場の片隅で、と畜が行われるこの国では、命を食べていることを、誰もが理解し受け入れていた。それは、肉を食し、薬を飲み、化粧品で装うことが、多くの動物の命によって支えられていることを受け止めきれていない日本の人々のために、動物の命を奪うことが日常だった私に、心の安寧を与えてくれた。
学生時代から、南アジアに心惹かれてはいた。でもそれを決定づけたのは、このバングラデシュの旅だった。会社で医薬品研究に携わっていた私は、この旅をきっかけに南アジアの農村にどっぷりとつかっていった。畑や田んぼを牛の力を借りて耕し、ヤギを飼い、羊を束ね、ニワトリを放つ。人びとの暮らしは常に家畜とともにあるが、近しいその存在への感謝は、その命を自らの命を続けるために食することで示される。家の庭先で、市場の片隅で、と畜が行われるこの国では、命を食べていることを、誰もが理解し受け入れていた。それは、肉を食し、薬を飲み、化粧品で装うことが、多くの動物の命によって支えられていることを受け止めきれていない日本の人々のために、動物の命を奪うことが日常だった私に、心の安寧を与えてくれた。
 バングラに初めて足を踏み入れてから何年もたって、私は南アジアの農村を学び教えるようになった。そして昨年、初めて学生たちを連れてバングラデシュに赴いた。村を歩き回った帰り道に市場でヤギを買い、宿舎の中庭で屠った肉を夕食のカレーにしていただいた。ヤギの命が失われていく瞬間を必死に見守っていた学生たちは、夕食の席で、目の前に出されたカレーを手でかき混ぜその肉を噛みしめるようにして食べた。命を食べていることを、日本で育った普通の若者たちがきちんと受け止めてくれている。
バングラに初めて足を踏み入れてから何年もたって、私は南アジアの農村を学び教えるようになった。そして昨年、初めて学生たちを連れてバングラデシュに赴いた。村を歩き回った帰り道に市場でヤギを買い、宿舎の中庭で屠った肉を夕食のカレーにしていただいた。ヤギの命が失われていく瞬間を必死に見守っていた学生たちは、夕食の席で、目の前に出されたカレーを手でかき混ぜその肉を噛みしめるようにして食べた。命を食べていることを、日本で育った普通の若者たちがきちんと受け止めてくれている。
辛かっただろう体験を、食べる力に変えている。バングラデシュの深い懐は、ずっと昔の私だけでなく、今を生きている学生たちも変えるんだ。私たち日本人が、バングラデシュから教えてもらえることは、まだまだある。
 <プロフィール> 秋吉恵(あきよし・めぐみ)
<プロフィール> 秋吉恵(あきよし・めぐみ)
立命館大学教員。インドで獣医師として働く中で感じた限界をきっかけに専門を社会開発に転じる。解決の糸口を、人々が本来持つ可能性を発揮できる社会づくりに求め、その実現に向けて南アジアのみならず日本の農山漁村の人々や大学生とも関わりを広げている。
<シャプラニールとの関わり> シャプラニールの会員になって20年以上。2012年より理事。
この記事の情報は2016年8月19日時点です。










