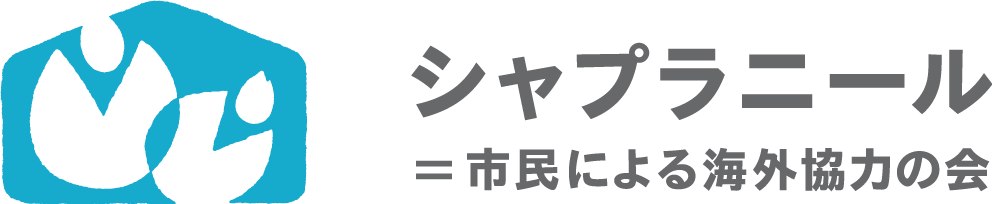理事・評議員からのメッセージ
シャプラニールの運営にかかわる理事・評議員から、ご自身の活動や専門性の高いトピックに焦点をあててレポートいただきます。タイムリーな話題、広い視野から多角的な海外協力の今をお伝えします。
人が移動する時代における日本の多文化共生
N P O法人国際活動市民中心コー ディネーター/シャプラニール評議員 新居 みどり

PROFILE
にい・みどり
京都府出身。青年海外協力隊員としてルーマニアに赴任。帰国後、大学と同大学院で多文化共生について学ぶ。東京外国語大学、国際移住機関コンサルタントを経て、2011年にNPO法人国際活動市民中心(CINGA)に入職、現在に至る。
「取り残さない、その小さな声を。」このシャプラニールのスローガンは、私の心の中心に響くことばです。私は25年前に青年海外協力隊として東欧ルーマニアで活動をしました。そこでは、多民族地域における日本文化を通した異文化理解教育と、ストーリートチルドレン(極寒のルーマニアではマンホールチルドレンと呼ぶ)の子どもたちのサポートをしました。3、4歳の子たちが空腹を紛らわすためにシンナーを寒空の下、吸っている姿をみながら、無力でしたが生活向上のために精一杯活動をしました。帰国し、その後は日本国内に暮らす外国人住民支援のNPO法人国際活動市民中心(CINGA)で働いています。
CINGAは、2004年から外国人相談と地域日本語の2つの柱を中心に、弁護士や行政書士、日本語教師など専門性を持った市民が集い活動をしてきました。2010年以降は、在住外国人の増加を背景に、事業規模が拡大し、外国人相談センターなどを受託して、事業展開をしています。

日本国内における小さな声を聞く
いま、相談の現場から見つめるとき、気になるのは家族に連れられて日本にくる南アジアの子どもたちの存在です。未成年の子どもが親族を頼って来日し、その親族が経営する劣悪な工場で働かせられているのではないか、女の子ということが理由で、中学校への進学を親から止められているのではないか、そのような相談が、地域で日本語や学習支援をするボランテイアさんたちから寄せられます。
日本においても、厳しい環境で暮らす外国ルーツの子どもたちが存在していること。その背景には、法律の壁やことばの壁、また周囲の日本人との間の心の壁など、多様な障壁があり、子どもたちのこえは、ますます遠く小さく届きにくくなっているのではないか。いま、この日本国内における在住外国人、とりわけ、子どもたちのために、国際協力NGOと地域の外国人支援団体が協力していく必要がある、そのように私は強く思います。どのようなことができるか、皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。

会報「南の風」305号掲載(2025年3月発行)