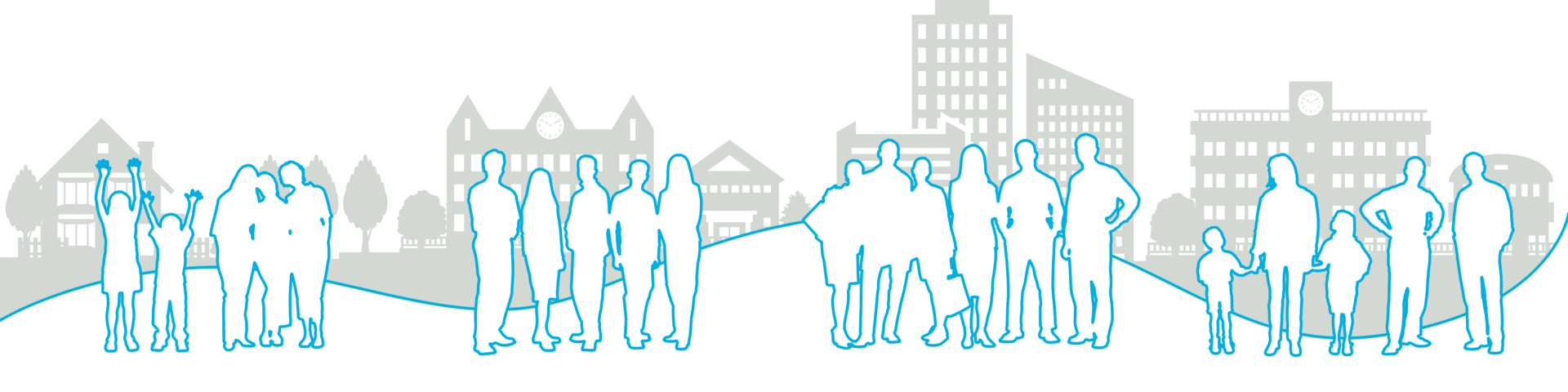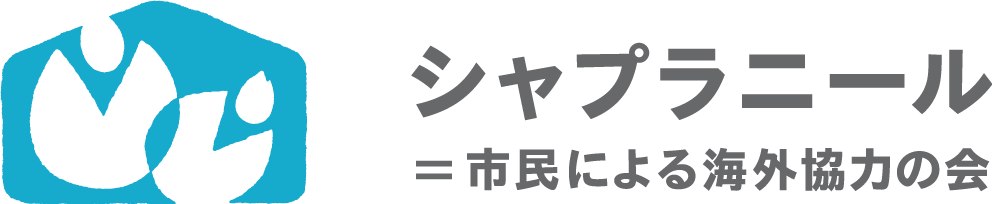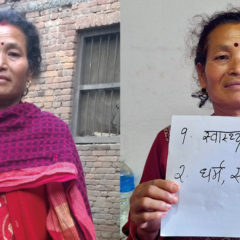本ネパール大地震・緊急救援&復興支援は終了しました。また、後継のカトマンズ盆地内住宅密集地の復旧・復興支援事業を実施した「ネパール大地震・復興&防災支援」も2019年10月に終了しました。ご支援いただきました多くの皆さまに感謝申し上げます。
2015年4月25日(土)現地時間11時56分、ゴルカ郡(カトマンズより西へ80km)を震源としたマグニチュード7.8の大地震は死者8,891名、倒壊家屋893,509戸(2015/9/28時点)という甚大な被害を引き起こしました。
多くの援助機関が撤退する中、20年間ネパールで活動を続けてきたシャプラニールは、地震発生翌日に緊急救援活動実施を決定。その後、復興支援を2019年10月まで継続して行いました。
緊急救援・復興支援活動 内容
■ 緊急救援活動(発災〜2015年6月初旬)
地震発生翌日に緊急救援活動実施を決定し、2015年5月末までの間に計6名を現地に派遣し、カトマンズ事務所長、現地スタッフと合流し、すぐに物資配布を中心とした救援活動を実施。
 物資配布の様子
物資配布の様子
- 緊急救援活動(発災〜2015年6月初旬)詳細
- 約20年にわたってネパールで活動してきた経験、ネットワークを活かして、支援が届かない地域、人々への支援を意識して救援活動を進めました。この間、日本では多くの個人、団体の方からご寄付をいただけたことで、迅速な安心して救援活動を進めることができました。
その結果、主に毛布約2,700枚、マットレス2,430枚、ビニールシート約1,900枚、食糧2,330世帯分を緊急救援物資として配布し、約5,400世帯へ支援することができました。カースト制度の残るネパール社会の中で阻害されがちなダリット(不可触民)の人々や寡婦へ支援が行きわたるよう意識をしながら、地域の行政、現地のNGOと協力して公平に配布を行いました。遠隔地だけでなく、比較的カトマンズに近い地域でも支援から取り残されている村もあり、そういった地域へも必要な支援を届けました。
| 期間 |
地域 |
世帯数 |
活動内容 |
| 5/1 |
チトワン郡 |
|
郡病院へ医薬品キット54セットを提供 |
| 4/30〜5/7 |
チトワン郡4村 |
718世帯 |
被災者への物資の配布
・ビニールシート329枚
・毛布270枚
・食糧セット(5人家族×5日分)370セット
(米12kg、ダール豆2.5kg、塩1kg、大豆油1L、大豆たんぱく250g、香辛料一パック、石鹸一つ) |
| 5/13 |
チトワン郡3村 |
63世帯 |
支援物資購入のためクーポン5,000Rsクーポンを山崩れの危険があり移住勧告が出された63世帯へ配布 |
| 5/1, 5/2 |
カトマンズ郡
キルティプール市 |
500世帯 |
食糧セット(5人家族×5日分)500セット配布
救護所への医薬品提供 |
| 5/4〜 |
カトマンズ郡 |
|
児童労働削減の活動のパートナー団体CWINに集まった若者ボランティアのコーディネーション、管理をピースボートにやってもらえるよう橋渡しを実施。 |
| 5/6 |
ヌワコット郡
トゥプチェ村 |
110世帯 |
食糧セット(5人家族×5日分)100セット配布 |
| 5/12 |
ラスワ郡
ヤルサ村 |
1,350世帯 |
米30Kgを1,350セット配布 |
| 5/15 |
ラメチャップ郡2村 |
1,363世帯 |
シェルターキットを1,363世帯へ配布
(キット:ビニールシート1枚、マットレス1枚、ロープ1本 、毛布1枚) |
| 5/11, 5/19 |
カブレパランチョーク郡2村 |
1,254世帯 |
村の緊急救援物資購入予算のうち、足りない部分を支援することで村の被災全世帯が物資配布を受けられるよう支援
・毛布1,067枚
・マットレス1,067枚
・ビニールシート187枚 |
■ 復興支援活動-初期-(2015年6月〜2016年3月)
復興支援初期フェーズでは、地域(丘陵地帯/カトマンズ盆地内)の偏りなく、支援の届いていない場所へ出向き、仮設住宅、コミュニティラジオの再建等今後の防災事業へのつながりを意識した活動を実施。
 完成した仮設住宅
完成した仮設住宅
- 復興支援活動(初期)(2015年6月〜2016年3月)詳細
-
| 活動 |
地域 |
対象 |
概要 |
| 仮設住宅支援 |
タナフン郡 |
全壊家屋500世帯 |
政府の指定する被災14郡から外れて支援が届いていない地域などで、仮設住宅建設時に屋根や壁に使用できるトタン板を配布した。 |
| オカルドゥンガ郡 |
全壊家屋310世帯 |
| コミュニティ・ラジオ再建支援 |
シンデュパルチョーク郡、ダディン郡、ラスク郡、ゴルカ郡、カブレ郡、ラメチャップ郡 |
コミュニティラジオ局 |
ネパールの生活に密着し、情報を得るのに欠かせないコミュニティラジオの放送局が被災し屋外のテント等で活動している状態だった。機材購入などにより10カ所のラジオ局の復旧を支援した。 |
| チトワン郡生活再建支援 |
チトワン郡 |
移住勧告が出された24世帯 |
家屋が倒壊し、土砂崩れの危険から移住勧告が出された山間部の住民の移住先の住居やトイレ建設などの生活再建支援を行った。 |
■ 復興支援活動(2016年11月〜2019年10月終了)
復興活動の多くは被害が大きかったとされる地方部に集中し、都市部の被災者が取り残されるという状況が発生しました。古いレンガ造りの建物が密集する地域では多くの住宅に被害が出ていますが、奥まった通りに集中しているため大通りからは見えず、「カトマンズ市内はあまり問題ない」という印象を与えていることも一因です。
私たちは今回の被災体験の学びを、将来の災害に備えた災害に強い地域づくりに活かすべく、カトマンズ市とラリトプール市で復興支援を継続することを決定。援助の手から取り残された地域で、生計手段・インフラ支援等、元の生活を取り戻すための支援を行い、2017年からは防災学習センターの運営や地域住民への啓発活動を通じて、地震に対する備え、建造物のリスク削減、非常用持ち出し袋の重要性等を伝え、地域の意識向上を目指しました。
現地パートナー団体:SOUP(スープ)
1992年、ボランティアによって設立されたNGO。カトマンズ市とラリトプール市で、女性と子どもを中心に支援活動を行っている。
 地震の仕組みを紙芝居で理解してもらう学校での取り組みの様子
地震の仕組みを紙芝居で理解してもらう学校での取り組みの様子
- 復興支援活動(2017年3月〜2019年10月終了)詳細
- 実施内容《取り残された地域の人々が1日も早く元の暮らしに戻るために》
- 被災者の生計手段支援:地震で生計手段を失った、収入が十分に得られていない被災者の中でも、社会的に弱い立場の人を優先した75名の被災者に対し、新しい事業を始めたり事業を再開したり、収入を向上したりするために必要な支援を行う。
- インフラ支援:集落が共有して使っている水場や細い道、広場といったインフラを修繕する復興支援を行う。
- コミュニティセンターの運営:被災によって抱えた困難を誰かに話すことができ、生活再建に関する情報が簡単に手に入る場所を提供するために開設したコミュニティスペースの運営を、地域の情報を集め、発信する役割を担うコミュニティFMラジオ局と協同で継続。情報提供のほか、傾聴やイベントを通じて、厳しい非難生活の中で抱える不安や辛さからひと時でも解放されるような憩いの場を作り出す。
- 被災学生の教育支援:被災による経済的困難から入学、通学が難しくなった青年の大学、専門学校の学費支援を行う。
実施内容《将来起こりうる地震の被害を軽減するために》
- 防災・減災の取り組み:
防災学習センターを運営し地域住民の防災意識向上を目指す。ご近所付き合いの集落単位で地域防災リーダーの育成を行い、やハザードマップの作成、救急救命用具の設置、避難用品の備蓄といった防災・減災活動を行う。
| 活動 |
地域 |
対象 |
概要 |
| 防災・減災活動 |
カトマンズ市、ラリトプール市 |
カトマンズ盆地内の住宅密集地域 |
被災者の生計向上支援、集落の共有インフラ修繕、防災リーダー育成、防災地図作成、地震時の経験のまとめなど
|
| コミュニティスペースの運営 |
シンドゥパルチョーク郡、ダディン郡、ゴルカ郡、ドラカ郡、カブレ郡 |
被害の大きかった地域の住民 |
住民が交流してリラックスしたり、情報を得、発信したりできるスペースをコミュニティラジオ局に併設して運営する。 |
| 被災学生の教育支援 |
カトマンズ市近郊 |
被害の大きかった地域の住民 |
被災による経済的困難から、入学・通学継続が難しくなった青年の大学、専門学校の学費支援を行う。 |
成果
地震発生直後から食料や物資の配布等の緊急救援、続いて生計手段の機材支援などの復旧・復興支援を行い、約6500世帯に支援を届けることができました。
2019年度には、復興支援3カ年の活動成果をはかるために、終了時調査を実施。結果、調査の回答者や回答者の家族が災害リスク削減に関する研修を受けたり、大地震など災害発生時の避難場所や連絡手段について家族と話し合ったりするなど、回答者の55%が防災の取り組みに関わっていることが確認できました。また、回答者の46.5%が、大地震に備えができていると考え、地震に対する恐怖心が和らいだと回答しています。いずれも、事業初年度に実施したベースライン調査結果と比較して、10%以上の上昇となっています。
さらに、地震がどのように発生するか、避難場所、応急手当用品の備蓄場所、コミュニティ災害管理委員会の活動について知ることができた、自宅に緊急連絡網や非常用持ち出し袋を常備している、と回答した割合も、事業開始前と比較して上昇していることも判りました。このように、住民の間で次の災害に備えて、日頃から防災の取り組みを行うことの重要性が認識されるようになり、また各地域の防災管理員会による活発な働きや学校での防災教育が積極的に実施されているなど、住民の防災知識の定着が確認されたため、本事業は2019年10月をもって終了することとしました。
ブログ一覧
あなたにできることが、必ずあります。
あなたにできることが
必ずあります。
「誰も取り残さない社会」、その実現へ。
シャプラニールと一緒に、アクションを起こしませんか。
「誰も取り残さない社会」その実現へ。
シャプラニールと一緒に、
アクションを起こしませんか。